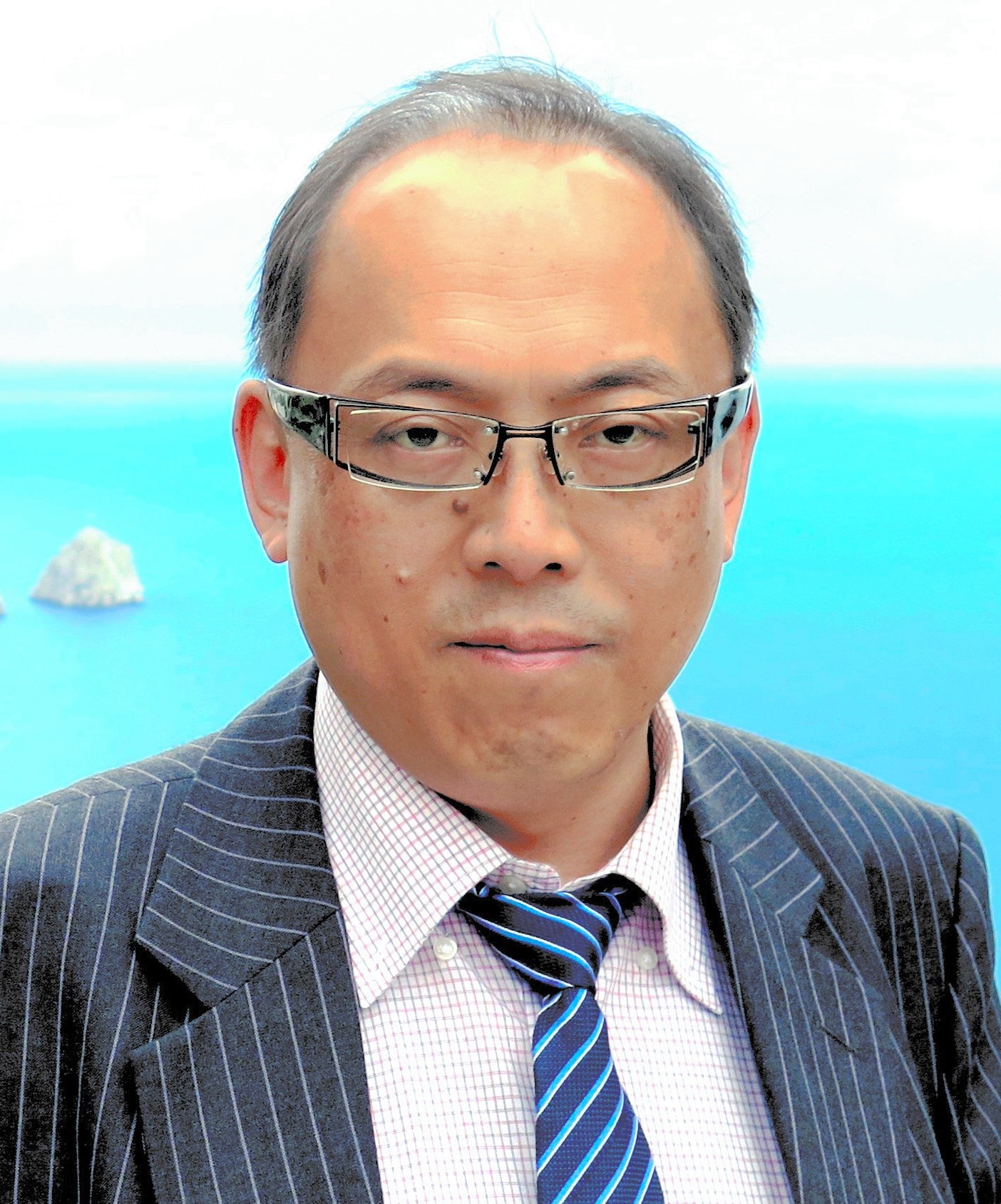コメンタリー
「中東の『恐怖の均衡』が崩れた」 フランス国際関係研究所専務理事に聞く

中東は激動のさなかにある。ハマスとイスラエルとの衝突から始まった戦争はイランに波及し、米国によるイランの核関連施設への攻撃に発展した。この混乱はどこまで広がるのか。中東の枠を超えるのだろうか。
フランス国際関係研究所(Ifri)の専務理事兼外交専門誌『ポリティーク・エトランジェール』編集長のマルク・エケル氏(44)に聞いた。
(パリで2025年7月1日、聞き手は東京大学先端科学技術研究センター特任教授・国末憲人)
――イスラエルとイランの間で戦争が勃発し、米国がイランを攻撃しました。状況の変化があまりに速く、ついていけません。この事態はどこへ向かうのでしょうか。
少し距離を置いて状況を見つめ直した方がいいでしょう。少なくとも2023年10月7日までさかのぼる必要があります。この出来事(ハマスのイスラエル攻撃)は中東の力学を根本から変えたからです。
現在(2025年7月)と2023年10月7日以前の状況を比較すると、勢力均衡(バランス・オブ・パワー)が大きく変化したとわかります。かつてのイスラエルとイランの関係は一種の「恐怖の均衡」に基づいていましたが、それが崩れたのです。イスラエルはこんにち、地域の支配的な存在となりました。イランは著しく弱体化しています。
2023年10月7日以前、イランはいくつかの強みを持っていました。第一に「代理勢力(プロキシ)」、いわゆる「抵抗の枢軸」です。中でも最も強力だったのはヒズボラですが、他にも多数存在しました。ハマス、イスラム聖戦、シリアやイラクのシーア派民兵、イエメンのフーシ派などがその例です。また、国家主体ではあるものの、シリアのバッシャール・アル=アサド政権もイランと非常に近く、シリア内戦中はヒズボラの支援を受けていました。
2023年10月以降、イスラエルはこれらすべての代理勢力と戦争状態に入りました。これは「七つの戦線での戦争」とも呼ばれています。イスラエルの戦略家たちによると、そのネットワークの中枢にいるのはイランです。イランが攪乱能力を持ち続ける限り問題が真に解決することもない、との認識が明らかでした。
代理勢力に加えて、イスラエルは2点について強く懸念を抱いていました。イスラエル全土を射程に収めるイランの弾道ミサイルと、イランの核開発計画の進展です。近年はウラン濃縮が著しく進み、これは国際原子力機関(IAEA)の報告でも言及されています。
2024年10月、ヒズボラを著しく弱体化させ、イランの防空能力を削いだイスラエルの指導層は、イランの核開発を遅らせ、さらには排除する「歴史的なチャンス」が到来したと感じ取りました。そのような感触は、米大統領選でのドナルド・トランプの勝利によってさらに強められたのです。選挙の直前、私はイスラエルの安全保障関係者と意見を交換する機会を持ちました。その根幹は次のようなものでした:
「カマラ・ハリスが当選すれば、彼女が米政権に就く2025年1月までの間に、イスラエルはイランへの作戦を急いで実行に移すかもしれない。新たな民主党政権がイスラエルへの武器供与を止める恐れがあるからだ。一方で、もしトランプが当選すれば可能性の枠が広がり、時間に余裕ができる。その間に、イスラエルはトランプに対し、軍事作戦に加わるよう説得もできる」
実際にもそうなったのです。
イスラエルによるイランの核開発計画を標的とした作戦は、従ってまったくの驚きではありませんでした。そのような行動を起こす可能性が高まっていると、何カ月か前から私たちは感じていました。予想外だったのは、標的が核施設だけでなく他のインフラにも拡大されたこと、そして体制転換をにおわせる言説が出てきたことです。
――つまり、米大統領選の前からこの攻撃はしっかりと計画されていたということですか。
計画されていたとまでは言いませんが、検討され、準備されていたシナリオの1つだったとはいえるでしょう。
数年前のことですが、私はイスラエルの国防の中枢にいる官僚に「中東の特定の国への介入計画が存在するか」と尋ねたことがあります。どの国だったかは覚えていませんが、返答は即座にこう返ってきました。「この地域のすべての国に対して計画はあるよ」と。
この返答を「拡張主義的な野望の証拠」と解釈すべきではありません。二つの意味合いを理解した方がいいでしょう。1つは、計画すること自体が軍事的伝統の一部であることです。多くの国では、たとえ起きる可能性が低くとも、将校たちがさまざまな軍事作戦のシナリオを想定しています。もう1つはイスラエル独自の事情で、常に最悪の事態に備えなければならない敵対的な環境から来る切迫感があります。
従って、イランに対する作戦計画が存在したのも間違いありませんし、シリアに対するものもあったはずです。バッシャール・アル=アサド政権が崩壊した際、イスラエル軍がすぐに対応できたのも、事前に介入計画が整備されていたからでした。計画担当の将校の仕事とは、予測不能な出来事に備えておくことです。何か突発的な事態が起こった際、軍は政治指導者に対して、複数の選択肢を迅速に提示できなければなりません。そのうえで、最終的にその計画を実行するかどうかは、状況や国益を慎重に考慮したうえで政治家が判断するのです。
今回のイスラエルの軍事介入では、軍(特に空軍)と、モサドが担う情報機関の部門との緻密な連携が見られました。こうした連携は、数週間や数カ月で成し得るものではありません。
――2020年以降、イスラエルと複数のアラブ諸国との間で結ばれた「アブラハム合意」は、両者の関係を急速に深化させました。その結果、パレスチナ問題は脇に追いやられ、イスラエルは中東地域において主要な外交アクターとなりました。それなのになぜ、イスラエルは軍事的手段に訴える必要があったのでしょうか。
アブラハム合意を結んだのはアラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、スーダン、モロッコの4カ国です。しかし、この合意はアラブ世界の一部、それ以上にイスラム世界の一部から、冷ややかに、あるいは敵意をもって迎えられました。敵意の一因は、まさにパレスチナ問題が棚上げされたことでした。
このパレスチナ問題は、2023年10月7日に劇的な形で再浮上しました。イスラエルは完全に不意を突かれたのです。それまでのイスラエル歴代政権は、アブラハム合意の枠組みを非常に好意的に捉えていました。それは、「穏健なスンニ派国家」と協力を進めることを可能にし、失敗と見なされるオスロ合意(和平プロセス)の枠組みに取って代わるものとなり得たからです。
イスラエル側には、このスンニ派との連携がイランの影響力に対抗する軸となり得る、との期待もありました。しかし、アブラハム合意の署名国はこの点で非常に慎重でした。彼らにとって、イスラエルへの接近は特に商業面での関係強化の方法であり、また中東における広い意味での平和構築の一環に過ぎず、イランに対抗する同盟を結成する意図はありませんでした。署名国はパレスチナ問題についても、イスラエルと交流を保ち、和平の枠組みをつくることが、結果的にパレスチナ人を助けることになるだろうと考えたのです。実際には、そうはなりませんでした。ガザで起きたことがアラブ世界の憤激を引き起こしたことから、いくつかの署名国は不安定な立場に追い込まれています。
イスラエルは、イランとその代理勢力に対して軍事的な勝利を収めたと言えるかもしれません。ただ、ガザでの戦争の進め方によって、国際世論は全般的に、イスラエルに背を向けることになりました。イスラエルにとって今の最大の課題は「この戦争をどう終わらせるか」になっています。
フランスとサウジアラビアは、「二国家解決」を実現するための国際会議を7月末に開催する計画を立てました。しかし、イスラエル政府はこの種の取り組みに全面的に反対しています。従って、現在はまさに袋小路に入り込んだように見えます。右派と右翼の支配によってイスラエル政府は「とことんやる主義」に陥っていますから。政府中枢の一部の閣僚は、ガザのみならず、ヨルダン川西岸の広範な部分に対する野心を隠しません。
現在の情勢は極めて複雑です。力の均衡が変化したからです。イスラエルは地域的に支配的な地位を確立し、今のところトランプ政権の支援も得られています。実際、(トランプは)駐イスラエル大使として入植支持派の人物を任命したほどです。パレスチナ人たちは深刻な悲劇に直面し、極度に弱体化しています。国際社会は分裂し、無力感をかみしめています。
――状況改善の兆しはどこかに見られますか。
いいえ。イスラエル側は、軍事的手段によって解決策が得られると考えています。最も極端な解決策は、ガザからの大量の住民移動です。実際、ドナルド・トランプは、パレスチナの飛び地を「リビエラ」に変えるという計画を語った際に、この可能性を排除しませんでした。しかし、それはやはり想像を絶することであり、非現実的です。ほぼすべての欧州諸国も、もちろんアラブ諸国もこれに反対しています。それはまた、国際刑事裁判所(ICC)に関するローマ規程の第7条に定められている「人道に対する罪」にも該当するでしょう。
ただ、今日において国際法はどれほどの重みを持つでしょうか。戦争犯罪や人道に対する罪という概念にどれほどの意味があるのでしょうか。トランプ政権は国際刑事裁判所に制裁を科しましたし、中国もロシアもローマ規程には参加していません。いまや大国間競争の時代が復活し、力による支配が新たな規範となっているように見えます。一方で、紛争の種類によっては軍事力だけだと解決できないこともわかっています。軍の行動には限界があるのです。
――イスラエルやアメリカによる攻撃を見る限り、イランの反撃はかなり限定的に思えます。
イランは数百発の弾道ミサイルと数百機のドローンをイスラエルに向けて発射しました。イスラエル国内では大きな被害が出ましたが、死者数は「わずか」29人でした。イスラエル軍がイラン国内で多数のミサイルや発射装置を破壊したことを考えると、イランにはもはや、イスラエルの防空システムに打撃を与える力が残っていないかもしれません。この「12日間の戦争」以前からこの国はすでに弱体化していましたが、現在はその傾向がさらに進行しています。イランの空は丸裸で、今後イスラエルによる新たな空爆の可能性も否定できません。
イランの核開発計画の現状を正確に見定めるのは困難です。ドナルド・トランプはこの計画が壊滅状態になったと主張していますが、多くの専門家はそれを否定しています。60%まで濃縮された約400キロのウランがどこにあるのかも分かっていません。核開発計画は確かに遅らせることができましたが、どれだけ遅れたのかは定かでありません。イランは恐らく、核兵器の取得を依然として目標としていると思われます。イランの他の抑止力――代理勢力(プロキシ)や弾道ミサイル――が機能しなくなっているからです。イスラエルは、イランが核兵器を手に入れるのを黙って見過ごすことはないでしょう。彼らはイランを、レバノンと同様の「必要に応じて限定的に攻撃できる場所」と見なす可能性があります。
多くの識者はベンヤミン・ネタニヤフの司法問題を指摘し、戦争を継続することで彼が権力を維持していると見なします。私はしかし、この説明は不十分だと思います。首相は、ユダヤ民族を守るという歴史的使命を担っていると信じ込んでおり、イランや「抵抗の枢軸」(反イスラエル連合)が唱えるイスラエル壊滅の呼びかけを極めて深刻に受け止めています。彼は、イランの体制をナチス・ドイツに例えることさえためらいません。迫りくる存亡の危機に対して、いかなる妥協も不可能だと考えています。

――このような変化に対して、ヨーロッパ諸国はどんな姿勢で臨んでいますか。
2023年10月7日以降に欧州で顕著なのは、一枚岩になれないことと、無力感です。EU加盟国間同士でも、各国内部でも、深刻な意見の相違があり、政治的分断線が明確です。大まかに言えば、左派に近づくほどパレスチナへの支持が強く、右派や極右に行くとイスラエルへの支持が強まる傾向です。フランスも、かつてド・ゴール将軍がアラブ世界との関係強化を進めたものですが、同様の傾向がうかがえます。
イランについては、2015年にウィーンで結ばれた合意「包括的共同作業計画」(JCPOA)にフランス、イギリス、ドイツ、EUなど8つの関係当事者が署名しています。その目的は、イランの核兵器保有を避けるためでした。英仏独はここ数年間、ウラン濃縮などによってイランが核開発を進めることに対し、非難の共同声明を複数発表しています。この観点から見れば、イスラエルの攻撃が欧州の目標と一致している面も、ないわけではありません。ただ、その方法は、ヨーロッパが望んだものではありませんでした。ヨーロッパが重視する方法は外交的手段であり、なすべきことをきちんと履行しているかどうか国際機関を通じて監視する手法です。だから、イスラエルがイランを攻撃した際に、欧州諸国は一種の当惑の様子を見せました。ドイツの新政権はイスラエル支持を表明しましたが、フランスと英国は自制や外交的解決を呼びかけました。ただ、明確には非難しませんでした。
――パレスチナ問題をめぐってはヨーロッパ内でも意見の違いが目立ちます。ただ、中東以外を眺めると、ウクライナ問題についてはある程度の結束があるように見えます。
ウクライナ問題については、より広い文脈で考える必要があります。たぶん、2025年2月に米副大統領のJD・ヴァンスがミュンヘン安全保障会議でした演説を思い出すといいでしょう。これは、多くの欧州人に衝撃を与えた演説でした。
それまでは、フランス大統領エマニュエル・マクロンが提唱する「欧州の戦略的自立」という主張を、欧州の多くの国は冷ややかに受け止めていました。EU加盟国のいくつかは、近い将来に米国の支援なしに欧州が自らを守ることになろうなどとは、考えもしませんでした。しかし、JD・ヴァンスが激しい演説を繰り広げ、ヴォロディミル・ゼレンスキーとのホワイトハウスでの険悪な会談や、ウクライナへの情報提供の一時停止が続いたことから、最悪の事態もあり得るのだと、人々は恐れました。
フランス大統領の立場は時に風刺の対象にもなりましたが、彼の主張は、欧州が外部に依存することなく行動する能力を整備すべきだというものでした。米国との決別を意味するわけではなく、米国の関与が大幅に減少する場合も含め、あらゆるシナリオに備えるためです。
ドナルド・トランプはホワイトハウスに返り咲いて以来、ウクライナ問題についてはコロコロと立場を変えています。米国がどれほど、どの程度の速さで関与を薄めていくかはわかりません。全体として見ると、EU諸国およびEU機関が提供しているウクライナ支援の総額は、米国をやや上回っているといわれます。ただ、米国が支援を完全に停止すれば、年間400〜500億ユーロ以上の追加資金が必要となります。これは、現在のヨーロッパ各国の財政状況を考えれば極めて重い負担です。加えて、いくつかの面、特に情報面では、米国が抜けた後を埋めるだけの力量を、欧州は持ち合わせていません。
わからないのは、トランプ政権が実際に何をするのかです。私は、ハーグで開かれた北大西洋条約機構(NATO)首脳会談の公開フォーラムに参加しました。そこでは、一部の専門家が「米国が情報提供を完全に止めると、米国自国の利益にも反する」と評していました。ただし、ドナルド・トランプは極めて衝動的な人物であり、政権の方針も日によって変わる可能性があるため、誰も確信を持てていないというのが実情です。
――非常に困難な将来が待っていそうです。
この複雑な状況下で、欧州の人々はやや熱に浮かされている感がありますが、行動しなければならないことも認識しています。「欧州の戦略的覚醒」や「戦略的な奮起」といった表現がよく使われます。実際には、NATOの「欧州の柱」を強化することになるでしょう。ハーグのNATO首脳会議では、加盟国が2035年までにGDPの5%を防衛支出に充てると約束しました。そのうち3.5%は純粋な軍事費にあたります。これは多くの加盟国にとって非常に大きな飛躍であり、厳しい予算上の調整が必要になります。
NATO首脳会議の首脳宣言では、「ウクライナの安全保障は同盟全体の安全保障のためだ」と明記されました。だからこそ、ウクライナへの支援もこの5%の枠内に含まれます。
ハーグには何人かのウクライナ代表も来ていました。彼らは疲れ果て、苦難に満ちているように見えましたが、外部からの支援には依然として大きな期待を寄せています。その期待が特に欧州に対して大きいのは、トランプ政権の気まぐれが当てにならないと知っているからです。
――国によって姿勢の違いがないでしょうか。例えばスペインは支援に対して躊躇しているといわれます。
スペインは特例措置を得るよう交渉していました。というのも、もしペドロ・サンチェス首相が5%の防衛支出目標を受け入れていれば、政権が崩壊しかねなかったからです。左翼政党「スマール」の党首は「目標に同意すれば連立を離脱する」と警告していましたから。他の国、特に多額の債務を抱える国も、この目標の達成は困難です。フランスの場合、マクロン大統領は欧州に迫る脅威を考慮して、防衛に対して一層の努力をしたいと考えていますが、一方で政府は財政健全化のための緊縮を求められています。
ロシアに地理的に近い国々ほど、防衛力への投資が進んでいます。いくつかの国ではすでに5%の目標に近づいており、特に旧東欧諸国の国民は、自らを守るためには防衛への投資が必要だと強く認識しています。スペインの国民は確かに、ロシアの脅威に対して、バルト三国の住民たちほど危機感を抱いていないのです。
――ウクライナでの戦争やイスラエル・パレスチナ紛争がある中で、ヨーロッパはなおインド太平洋問題に関与する余裕があるのでしょうか。
NATO首脳会議の首脳声明を読むと、2つの主要な脅威が強調されています。ロシアとテロです。テロといえばアルカイダや「イスラム国」(IS)の活動場所だったアフガニスタンとかシリアとかが思い浮かびますが、今やアフリカが国際ジハード主義運動の深刻な新中心地と見なされています。つまり、中東やウクライナだけでなく、南側も問題なのです。
ではインド太平洋地域はどうか。フランスは欧州諸国の中でも、この地域で最も活発な国の1つです。フランスはインド洋(レユニオン島など)や太平洋(フランス領ポリネシアなど)に領土を持ち、約160万人のフランス国民がこの地域に居住しているからです。つまり、フランスはこの地域に主権の問題を抱えています。また、経済的利害も抱えています。フランスの排他的経済水域(EEZ)の90%以上がインド太平洋にあるのです。
2025年5月末には、マクロン大統領がシンガポールでの「シャングリラ・ダイアログ」(アジア安全保障会議)」の開会演説に招かれました。彼は、欧州とアジアの現場が今や相互に関連していると指摘し、北朝鮮軍がロシア・ウクライナ戦争に関与していることを例に挙げました。その際、彼が発した一言は、いくつかの反響を呼びました。
「もし中国がNATOのアジア進出を望まないのであれば、北朝鮮が欧州で活動するのも妨げるべきだ」
もう一つ反応が多かったのは、ウクライナと台湾を比較し、国境の不可侵原則や二重基準の否定について重要性を強調したくだりでした。
フランス国際関係研究所(Ifri)アジアセンターは最近、「クレマンソー25」と名付けられた作戦に関するセミナーを開催しました。空母シャルル・ド・ゴールを中心としたフランス海軍の空母打撃群がインド太平洋地域に展開する作戦です。これは、現地でプレゼンスを示し、航行の自由や地域の安定、ルールに基づく国際秩序を維持しようとする強い意志と結びついています。この展開は、フランスの利害が真意迫ったものであり、そのためのプレゼンスを確保していることの証明です。ただ、私たちは同時に、力の限界や世界の複雑さ、さらには、本土から遠ければ遠いほどかかわり方も複雑になるという、軍関係者が「距離の暴力」と呼ぶ状態も十分認識しています。
――インド太平洋問題と言うとき、それは主に中国を指しています。ただ、今やトランプの米国やプーチンのロシアと比べると、中国の振る舞いはむしろ合理的に見えるほどです。
中国は大きな戦略を構築しています。2049年、すなわち中華人民共和国建国100周年の際に世界一の大国となることです。中国は軍事力を急速に増強しており、南シナ海での示威行動も頻繁です。台湾周辺での演習や軍事行動も継続しています。このように圧力を高めることは、深刻な懸念を引き起こしています。台湾で戦争が起これば、非常に好ましくない、壊滅的となりかねない影響を全世界に及ぼす可能性があるからです。
合理性という要素を指摘されましたが、その主体が「合理的」であるかどうかを判断するには、関係するあらゆる要素を考慮に入れなければならず、しばしば困難です。たとえば、経済合理性よりもイデオロギー(思想信条)が優先される場合もあるからです。
ここ数年の出来事を見ても、ロシアによるウクライナ全面侵攻や世界的な感染症の流行といった、起こり得ないと思われていた出来事が現実に起き、国際的な価値観を覆しました。起こり得ないと断言するのは、極めて慎重になるべきです。例え確率が低くても、「ブラック・スワン」(想定外の出来事)は起こり得るのです。
――だから、日本とヨーロッパの関係は重要なのですね。
まったくその通りです。米国の政治的変化に直面し、リベラルな民主主義諸国は羅針盤を失いつつあります。さらに、ポピュリズム勢力の台頭や政権の不安定化など、内部的な課題も抱えています。
しかし、それでもなお、価値観を共有し、ルールに基づく国際秩序への挑戦に対して屈服を拒否する国々がしっかりと存在します。日本や大多数の欧州諸国はそうした国々の一角を構成しており、リベラル民主主義を守り、国際秩序を強化するための共同戦線を構築すべきです。現在の国際情勢の中で、これらの国々の協力を進展させることが重要です。

Marc Hecker フランス国際関係研究所(Ifri)専務理事兼外交専門誌『ポリティーク・エトランジェール』Politique étrangère 編集長。パリ第1大学政治学博士で、パリ政治学院の教壇にも立つ。共著に『21世紀のジハード主義とテロ対策 20年の戦争』『フランスのインティファーダ?』『戦争2.0 情報世代の不規則な戦い』(いずれも未邦訳)など。テロ、紛争、中東情勢などに関する多数の英仏語論考がある。
同じカテゴリの刊行物
コメンタリー
2026.02.19 (木)
コメンタリー
2026.02.18 (水)
コメンタリー
2026.01.27 (火)