
東京大学先端科学技術研究センター創発戦略研究オープンラボ(ROLES、池内恵代表)とレバント戦略研究センター(LSC: Levant Strategic Centre、ザイド・イヤーダート所長)の共催で、「第2回日本・中東戦略対話」が11月19日、ヨルダンの首都アンマンのホテル「インターコンチネンタル・アンマン」を会場に始まった。日本やヨルダンをはじめ、十数カ国・地域から約150人が参加。この日は、中東に対する日本のかかわり方やエネルギー安全保障、シリア情勢などに関するセッションが開かれた。20日はパレスチナ自治区ガザの情勢などに関するセッションがある。
オープニング・セッションでは、グローバル・パワーのダイナミックな変化が起きつつある中東で、日本が何をなすべきか、日本に何ができるかをテーマに、4人が講演した。
レバント戦略研究センターのザイド・イヤーダート所長は、シリアの体制転換やガザでの戦争、イランの地位の変化など、ヨルダンやレバノン、イスラエル、キプロスなども含む地中海東岸地域「レバント」で起きつつある戦略的な変動の重要性を強調。この地域への日本の貢献に感謝を示すとともに、「パワーと原理と野望の大きな変化が起きつつある今、この地域にはもはや、旧来の地政学は通用しない。この変化は地中海や欧州だけでなく、アジアとも結びつく」と語り、日本のさらなる関与を促した。

イヤーダート所長
ROLESの池内恵代表は、中東が世界の他の地域との関係において独立性を増していると指摘。「地域で台頭しつつある新たな秩序について考えたい。日本の外交政策もこの変化に対応する必要がある」と述べた。

池内代表

浅利大使
ジャワード・アナーニー元ヨルダン副首相は、日本の中東への関与の歴史を回顧しつつ、これへの評価と今後に向けた期待について講演。「中東和平の支援者である日本にとって、ヨルダンは最適のパートナーとなるだろう」と、関係強化への期待を示した。

アナーニー元副首相
上村特使は、1981年のパレスチナ解放機構(PLO)アラファト議長来日やその後のオスロ合意、9.11米同時多発テロなどに外交官として取り組んだ体験を披露。慎重な形で始まった日本の中東外交が少しずつ進歩を遂げてきた経緯を語りつつ、「新たなチャレンジに対応するためには、さらに深い相互理解が必要だ」と述べた。

上村特使

宮島大使は、「ジェノサイド」の舞台となったアウシュヴィッツ強制収容所が位置するポーランドの大使となり、隣国ウクライナへのロシアの侵攻に対応した立場から、「ジェノサイドと呼ぶべきかどうかはともかく、多くの人命が失われたガザに近いこの地に来ることへの思うことが多い」と話した。

宮島大使

続いて、永井陽右・アクセプト・インターナショナル代表理事が、ソマリアやイエメン、エルサルバドル、コロンビアなどの現場での活動体験を語った。永井氏は、紛争地での対話推進や武装勢力からの離脱促進、元兵士の社会復帰などに取り組むNGOを運営する若手。「日本は援助などに関して得ている高い評価を利用して、ノルウェーのように紛争調停などで独自の役目を担うことができると言われる。ただ、そのためにはもっと現場で働く人が必要だ」と述べた。

永井代表理事

阿部俊哉・国際協力機構(JICA)評価部部長は、ガザやヨルダン川西岸で7年間活動し、さらに7年間東京でパレスチナ担当のデスクを務めた自らの体験を紹介。「1990年代はまだ希望があったが、徐々に低下し、現在はここ30年間で最低の段階だ。紛争後は通常、人道支援に続いて開発支援がなされるが、長期化した紛争状態にあるパレスチナでは、人道支援と開発支援の間を行き来する状況が続いている」と分析した。

阿部部長

第2パネルは「エネルギー安保と協力経済」。ヨルダンのイブラヒム・サイフ元エネルギー相、カワル・グループのカリム・カワル総裁、ヨルダン通信規制委員会のノーフ・アルシャブ長官、国際協力銀行(JBIC)の北村健一郎・ドバイ首席駐在員が討論した。
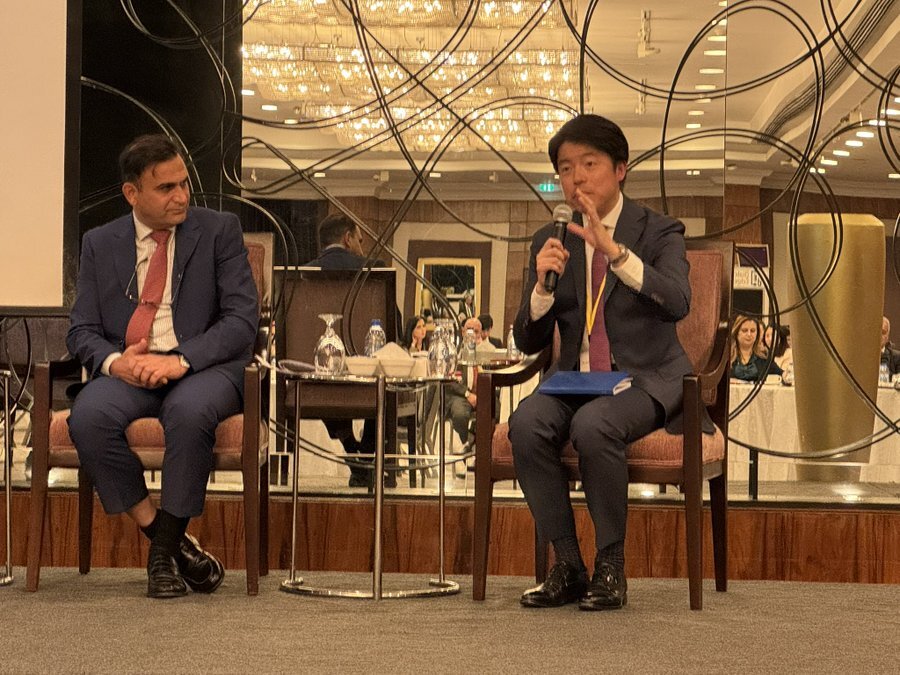
会場からの質問に応じる北村首席駐在員(右)
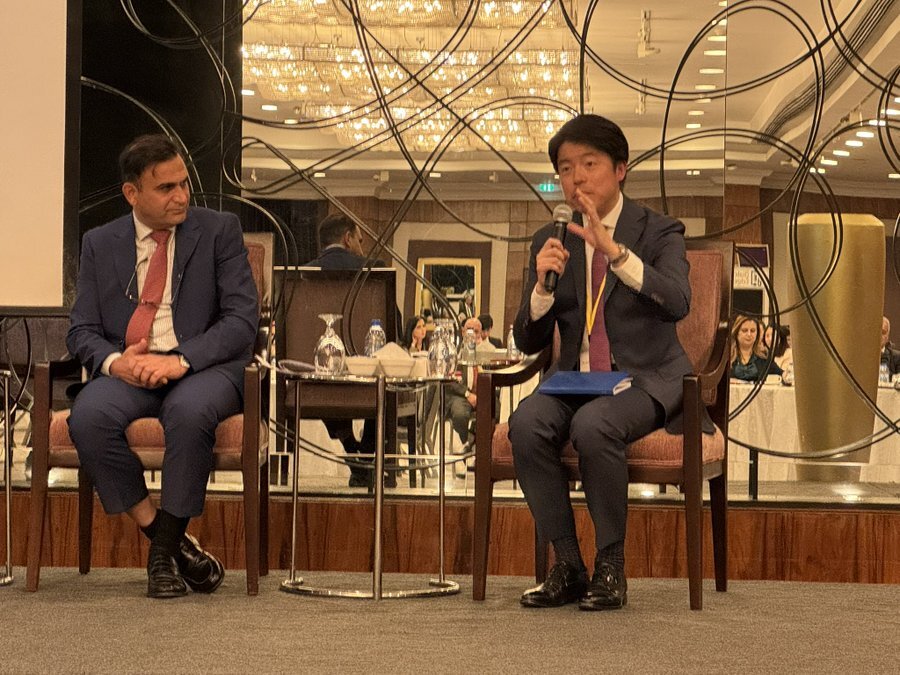
第3パネル「シリアとレバノン:強く合法的な政府をつくる」には、シリアの外相顧問ナジム・ガドビアン氏が参加し、「日本のソフトパワーが果たす役割に期待したい」と述べた。一方で、国土が完全には政府の統治下になっていないこと、領土の一部をイスラエルが占領することについて、懸念を表明した。

シリアの外相顧問ナジム・ガドビアン氏(右)

第4パネル「若者、復興、平和構築」では、アクセプト・インターナショナルの永井陽右さんがパレスチナから活動家や言論人を招き、若手による討論を展開した。西岸から参加した若手市民社会の指導者バトール・エリアン氏は「外国の組織が、初めてのパレスチナの諸勢力の対話を提起した」と、この試みを評価した。

永井陽右氏(左)

20日は、パレスチナ自治区ガザでの停戦やガバナンス、パレスチナ国家の将来、中東の安全保障秩序などをテーマにする4つのパネルとクロージング・セッションが開かれる。
「日本・中東戦略対話」は2024年5月12、13両日、アンマン市内のヨルダン大学で第1回を開いた。
同じカテゴリのニュース
お知らせ
2025.12.31 (水)
