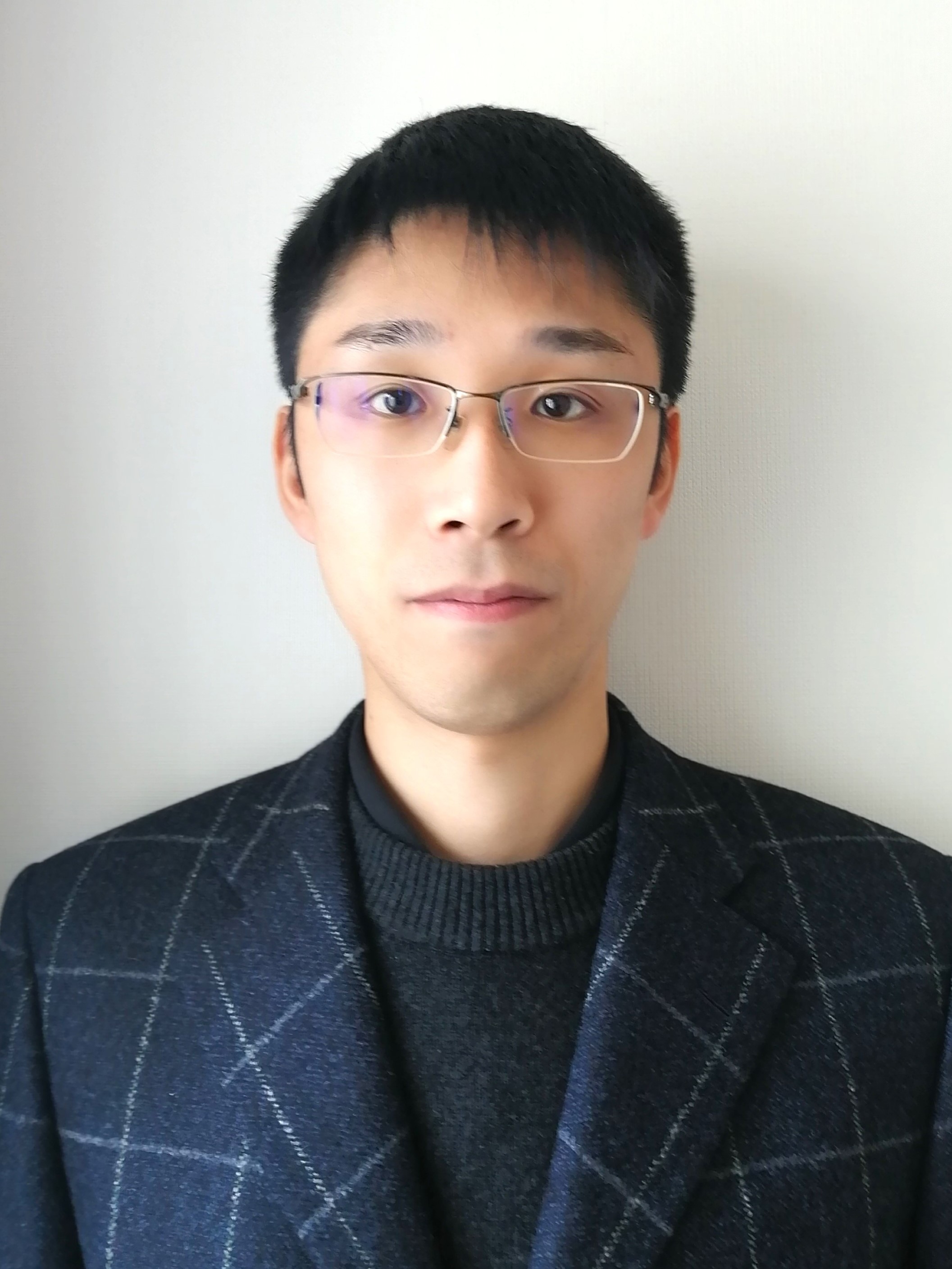コメンタリー
2025 / 03 / 30 (Sun.)
清水亮「ギャップに向き合うためにーー戦争社会学研究会例会「これからの『私たち』の歴史実践に向けて」から考える」(ROLES Commentary No.49)

1.はじめに——ギャップごしのコミュニケーション
「異なる価値観」や「分断」や「多極化」といった言葉が人口に膾炙する現代のグローバル多文化社会において、集団ごとにさまざまな知識や価値観のギャップがあることは一種あたりまえの前提となっている。そのギャップを前にして、互いに理解し得ないとあきらめて閉じ込もることも、簡単に理解したふりをしてギャップを隠蔽することも、通用しなくなっているとすれば、私たちはいかにして「ギャップごしのコミュニケーション」(後述)を模索していくかが課題となる。
本稿は、この問題意識を下敷きにしつつ、2024年6月に上梓した拙共編著『
戦争のかけらを集めて——遠ざかる兵士たちと私たちの歴史実践』(清水亮・白岩伸也・角田燎編、図書出版みぎわ)の議論の一部を整理して提示する。さらに、2025年1月26日に、東京大学先端科学技術研究センター創発戦略研究オープンラボとの共催で、駒場Ⅱキャンパスにおいて行われた、戦争社会学研究会2024年度第2回例会「
これからの「私たち」の歴史実践に向けて――『戦争のかけらを集めて』から始まるトークセッション」に至るまでの一連の刊行後のイベントを振り返る。
戦争のかけらを集めて——遠ざかる兵士たちと私たちの歴史実践』(清水亮・白岩伸也・角田燎編、図書出版みぎわ)の議論の一部を整理して提示する。さらに、2025年1月26日に、東京大学先端科学技術研究センター創発戦略研究オープンラボとの共催で、駒場Ⅱキャンパスにおいて行われた、戦争社会学研究会2024年度第2回例会「
これからの「私たち」の歴史実践に向けて――『戦争のかけらを集めて』から始まるトークセッション」に至るまでの一連の刊行後のイベントを振り返る。
「ギャップごしのコミュニケーション」という言葉を提起した歴史学者・保苅実は、オーストラリア先住民という、などの私たちが生きる世界——「近代」「西洋」などと呼ばれる——から遠い世界観に生きている「他者」とともに長期間のフィールドワークを過ごした。そこで出会った、私たちには一見荒唐無稽にみえてしまう歴史語り——大蛇が洪水を起こした、ケネディ大統領が村に来た——に対して、学術的観点からの排除でも、表面的な尊重でもなく、真摯に向き合う術を模索し続けた(『ラディカル・オーラル・ヒストリー——オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』岩波現代文庫、2018年)。長老たちの語りを聴き続けた保苅は、「和解」や「理解」といった言葉に安易に頼らずに、「ギャップごしのコミュニケーション」の積み重ねを通した「多元的歴史時空の接続可能性」を提案した。
たしかに拙編著『戦争のかけらを集めて』は、第二次世界大戦についての戦後日本の諸集団・個人の歴史実践についての論集である。しかし、少なくとも私は、戦争の歴史に関して単一の“正しい”歴史観の共有が不可能であることを半ば前提として、多元的な歴史観はいかにして有意義なかたちで共在しうるか、それをイメージすることは可能か、という課題を意識していた。
2.環礁モデル——ギャップを議論に組み込む
『戦争のかけらを集めて』のなかで、この点に最も関連する「エピローグ 環礁の屑拾い——「未定の遺産」化の可能性」の章をかいつまんで紹介しよう。戦後日本における戦争体験継承においては、体験者から非体験者へ伝達するという一方向的な「バトンリレー・モデル」が、典型的かつ支配的なイメージであるといえる。しかし、その伝達を担いうる体験者不在の時代を目前にして、そのイメージとは別の、非体験者が中心的な担い手となるような、オルタナティブな過去への向き合い方のイメージを提起しようとした。そこで、戦争関連の研究書を数多く手がけてきた編集者・岡田林太郎が、『戦争社会学研究』誌上で「バトンリレー・モデル」に替わるものとして提案した「環礁モデル」を援用した。岡田の「環礁」のメタファーは、体験者の記憶・記録が沈む「内海」を取り囲む、多数の独立した「州島」に非体験者がいるとする。非体験者は、戦争について知ろうとして、それぞれの「州島」から内海を眺める。ただ、それぞれの「州島」ごとに歴史観や価値観は異なることを前提としている点が重要だ。
たとえば広島・長崎の原爆という関心に対して形成された環礁の場合、内海には膨大な記録と記憶が眠っている。その周囲を囲む島にも、さまざまな意見を持った人が集まっている。おそらく、その意見を統合することは不可能であり、またそうする必要もない。たとえば原爆に対して、「二度と同じ被害を生まないために核兵器を廃絶しなければならない」という意見があるいっぽうで、「二度と同じ被害を生まないために核武装をしなくてはならない」という意見もありうるだろう。その意見の違いをお互いに排除しないために、形と大きさの違うさまざまな島がある。原爆問題の環礁にある島々は、その問題を共有し、少なくともそれについて語りたい・知りたいという人々を乗せている。
重要なことは記憶・記録を忘却しないことと、島間の交流・対話を否定しないことである。(岡田林太郎「〈環礁〉モデル試論―〈バトンリレー・モデル〉に替わるポスト体験時代のメタファー」『戦争社会学研究』第6巻、2022年、197~198頁)
ここで例示されているのは、歴史認識の違いを背景とした政治的意見のギャップである.
しかし、それは、戦争記憶継承という課題をめぐるギャップの一例にすぎない。まず戦前戦後の価値観の一変を背景としたジェネレーション・ギャップが知られており、さらに戦後80年にいたって親子世代よりも孫・ひ孫世代が中心となれば、世代間の溝は、断絶といってもよいほどに広がっている(この点の詳細は、清水亮「家族のなかの戦争記憶につながる」『戦争社会学研究』第9巻、2025年近刊)。さらに、学問分野間のギャップはもちろん、研究者と市民との間のギャップにどう向き合うか、という研究の公共性をめぐる問題もある。
『戦争のかけらを集めて』は、これらを意識しつつ、ベンヤミンや藤原辰史の議論をもとに、「バトンのような価値はないと思って体験者が捨ててしまったもの、手渡そうとしたのに誰も受け取らず放置されたもの、あるいは放棄させられたものを拾う」態度を示す「屑拾い」を、「環礁モデル」に描き加えた(262頁)。さらに、見田宗介の議論を援用して、「戦争体験という「遺産」の価値を、最初から定まっている(=既定)ものとして崇めるのではない。むしろ、その時々の問題状況のなかで、遺産を活用する者の側が発見し捉え直すものとみる」、「未定の遺産」という認識枠組みを提起した(257頁)。詳細は拙編著を参照いただきたいが、いよいよ体験者に頼ってはいられなくなる戦後80年において、戦争を一部の人々の狭い論争の場とすることなく、戦争の歴史について風通しよく議論する場を開く言葉を模索する試みであった。
3.他学問分野や市民との対話
拙編著は、研究成果の集大成というよりも、議論に火をつけるための書籍として、多少の蛮勇をふるって刊行した。そのぶん刊行を契機としていかに出来事を起こしていくかが重要だった。たとえば、戦後79年の8月には、
版元のブログに各著者がエッセイを書いた。その後の反応や企画は、
私のリサーチマップのブログにまとめている。「満洲の記憶」研究会大会のように歴史学の方々からコメントをいただく機会や、北極冒険家と厚木基地周辺を歩くイベントまで様々だ。それはできるだけ狭い専門領域に閉じこもらず、他学問分野や市民とのギャップごしのコミュニケーションを手探りしていく試みであったともいえるだろう。
版元のブログに各著者がエッセイを書いた。その後の反応や企画は、
私のリサーチマップのブログにまとめている。「満洲の記憶」研究会大会のように歴史学の方々からコメントをいただく機会や、北極冒険家と厚木基地周辺を歩くイベントまで様々だ。それはできるだけ狭い専門領域に閉じこもらず、他学問分野や市民とのギャップごしのコミュニケーションを手探りしていく試みであったともいえるだろう。
そうした流れのなかで、今回のROLESとの共催の例会「これからの「私たち」の歴史実践に向けて」があった。対面のみの開催で、申し込みは40人に達し、私のメモによれば会場に30人ほど来場した。コメンテーターに国際関係学の今泉裕美子氏、編著者側から教育史学の白岩伸也氏が登壇し、100分間確保されたフロアでの議論において、さまざまな世代や学問分野の研究者・市民からの活発なコメントが寄せられ、執筆分担者からの応答がなされた。特に歴史学者からは、「歴史実践」という概念が指し示す内容は、すでに歴史学が実践してきたことと重なり、その新しさはどこにあるか、というクリティカルな質問も寄せられた。社会学を専門とする私としては、隣接分野の蓄積に対する学びの不足がギャップを生み出してしまったことに反省するほかない。
個別の議論を紹介する余力はないが、私としては、次の3点の課題を自覚することができた。
第一に、非研究者の読者を巻き込むためのメタファーを中心とする問題提起の次には、学術的な蓄積に合わせた理論化という課題が待っている。特に、主要概念の「歴史実践」については、「歴史」については歴史学・歴史哲学などの議論を、「実践」については社会学・人類学などの理論を参照することが有益であるとの示唆を得た。
第二に、言語のみならず、身体的な歴史への向き合い方に対する注目である。戦場の恐怖や戦時下の銃後の日常の感覚に私たちはどう迫っていくのか、あるいはそれは不可能なのか、という課題である。個々人が書き残したエゴ・ドキュメントを読むという方法以外に、たとえば現場に足を運ぶ追体験を含めて、方法を多角化する可能性を模索していかなければならない。
第三に、戦争記憶継承ないし歴史実践という課題においても、個別の事実を知ることのみならず、研究を通して、その背後にある構造をいかに析出するかという課題を再確認した。たとえば、ある者は戦場の苦しみを記し、別の者は戦場を懐かしむとき、ある者が階級の低い兵で、別の者が階級の高い将校だとすれば、これらの歴史の断片を繋ぎ合わせて、戦争の受苦に関する「格差」という構造的な問題を析出しうる。私たちが知り議論すべきは、80年前の個別の事実の奥にある、見えない構造でもある。それは現代社会においても形を変えて継続する構造であることも十分にありうる。
4.おわりに——現代の戦争のかけらをどう集めるか
会場には、日本で暮らす難民の支援に携わってきた研究者も来場した。拙編著執筆中の2023年10月にはイスラエルのガザ侵攻がおき、本稿執筆中にウクライナ戦争は3年目を迎えた。拙編著でも、80年前の「あの戦争」との歴史的距離を強調しつつも、現代の戦争との向き合い方は模索中である。『戦争社会学研究』誌も、「特集2 ウクライナ問題と私たち」(第7巻、2023年)、「自由投稿 ウクライナ問題と私たち――会員の声」(第8巻、2024年)でジェンダーや計量的手法による社会意識調査といった多様な切り口での議論を表明したが、ウクライナ戦争への研究のアプローチは本格的着手に至っていない段階といえるだろう。
一方で、この原稿の執筆中はちょうど第二次トランプ政権の成立により「停戦」の気運がとにもかくにも高まっているが、もしも「停戦」が成立すれば、それはウクライナ戦争が「歴史」となる長いプロセスへのささやかな一歩になることを意味する。あるいは、すでに『戦争のかけらを集めて』で、「多様な過去の痕跡を収集し分析し組み合わせて、歴史を叙述する、終わりなき共同作業」」(7頁)と定義した意味でのウクライナ戦争の歴史実践は、すでに始まっているともいえるのかもしれない。
私は先述した『戦争社会学研究』の「ウクライナ問題と私たち」企画に寄稿していないが、もしも寄稿していたとしたら、開戦前の2020年に刊行されていた『ウクライナ・ファンブック——東スラヴの源泉 中東欧の穴場国』(平野高志、パブリブ)という教養ガイドブックを取り上げようかと思っていた。もちろん戦争前に刊行された本書に、ウクライナ戦争のことは書かれていないが、戦争前のウクライナで暮らす人々の生活や文化、政治経済のリアルなディティールを知ることができる(ロシア側の日常生活に触れるならば、たとえば小泉悠『ロシア点描——まちかどから見るプーチン帝国の素顔』PHP研究所、2022年がある)。何も知らない私は、遠い国の社会生活のあり方を学ぶことから始めるほかはない。おそらく戦争によってその多くが不可避の喪失や変動を被ったとしても、いやそれゆえにこそ、私はその大地に根づいた社会や日常を知る必要がある。それは目の前の出来事に対する一つの歴史実践であり、政治的・軍事的な戦況・外交の俯瞰的な解説とは別に必要な実践であると思う。
「21世紀を迎えたこのグローバルな時代に、自分とは無関係だと言いきれるほど遠い場所などありはしない」(『保苅実著作集 book1 生命あふれる大地』57頁)としたら、私たちは、世界の各所で現在も起きている戦争のかけらを拾う術も手探りで学び知らなくてはならないだろう。きっと、そこにまず必要なのは、ギャップを乗り越え(たつもりにな)ることではなく、保苅実が紹介したディペッシュ・チャクラバルティの言葉を借りれば、「ギャップにたたずむこと(stay with the gap)」、たたずみながらギャップを直視し続けることなのだろう。
Recent Publication
コメンタリー
2025.04.30 (水)