イベント情報
2024 / 12 / 13 (Fri.)
ROLES日豪抑止対話(JADD: Japan-Australia Deterrence Dialogue) 実施報告
ROLES日豪抑止対話(JADD: Japan-Australia Deterrence Dialogue)
実施報告
2024年12月12日、13日(於:キャンベラ)
鶴岡 路人(慶應義塾大学)
【実施目的・背景】
• 日本と豪州はともに米国の同盟国であり、日米間、および米豪間では政府間(トラック1)は当然のこと、民間(トラック2)や政府と民間(トラック1.5)など、さまざまな対話が存在している。しかし、日豪防衛協力が急速に進展するにも関わらず、戦略や抑止に特化した日豪間の確立された政策対話の枠組みは未発達だった。そのため、日豪抑止対話(JADD)を立ち上げる。
• 豪州では、特に政府内において日本留学経験者を含め、日本に詳しい人材が増えているものの、日本側では豪州の政治・外交・安全保障に詳しい人材が政府においてもシンクタンク業界、学界においても不足している。
• 日豪間では、それぞれが有する米国との同盟をいかに管理・発展させられるか、米国政治が大きく変化するなかで拡大抑止の信頼性をいかに維持できるか、米国のインド太平洋関与をいかに維持できるか、日豪が今後強化する長射程のものを含む攻撃能力(日本の場合は「反撃能力」)を同盟の抑止態勢においていかに位置付けるか、NATOや米韓同盟と異なり統合された指揮統制システムがないなかで、日本と豪州は米国との統合をいかに進められるかなど、共通の課題が多数存在している。
• 米英豪の枠組みであるAUKUSをインド太平洋地域や日豪防衛協力においてどのように扱うかも、今後重要な課題になる。全体としては、インド太平洋地域における抑止態勢の強化に日豪がいかに貢献できるかが問われる。
• それらを、単に政策課題として実務的、あるいはジャーナリスティックに議論するのではなく、学問的研究を基礎により深く掘り下げたい。さらにそうした継続的作業を通じて、日豪における政策志向の戦略研究、抑止研究を発展させることが日豪抑止対話の最終的な目的である。
• 「戦略対話」や「安全保障対話」ではなく、あえて「抑止対話」とするのは、テーマの拡散を防ぐためである。ただし、取り上げる課題は狭義の(軍事的な)抑止に限定する必要はなく、広く外交、安全保障、場合によっては経済安全保障や技術に関連するテーマも対象になる。それでも「抑止」という軸を維持し、議論の骨格を維持することを今回の対話の特徴としたい。
【実施形態】
• ROLESで実施中の「『西側』の論理の検証と再構築」研究会(西側研)が母体となり、豪州側について、今回はオーストラリア国立大学(ANU)の戦略・国防研究センター(Strategic and Defence Studies Centre: SDSC)がホストとなり、2024年12月12日にANU内で実施。
• 日本からは、JADD担当の鶴岡路人(慶應義塾大学准教授)の他、いずれも西側研メンバーの森聡(慶應義塾大学教授)、佐竹知彦(青山学院大学准教授)、寺岡亜由美(コロンビア大学研究員・講師:遠隔参加)が出席した。
• 豪州側は、Brendan Taylor(ANU教授、SDSCディレクター)、Stephen Fruehling(ANU教授)をはじめとして、10名以上が参加した。
• セッションは午前に2つ、午後に1つに加え、石破政権下での日本の外交・安全保障政策の展望に関する公開セッションを実施した。
• また、キャンベラ訪問の機会を活用し、翌12月13日には豪戦略政策研究所(ASPI)など訪問し、意見交換をおこなった。また、 JADD実施にあたっての、在オーストラリア日本国大使館からの支援にも感謝したい。
• 初回JADDでの議論を受けて、SDSCのCentre of Gravityシリーズで、日豪のJADD参加者の執筆による、日豪にとっての抑止の課題に関する報告書を2025年中に英語で刊行予定である。同報告書は、その後日本語に翻訳してROLESから刊行する。
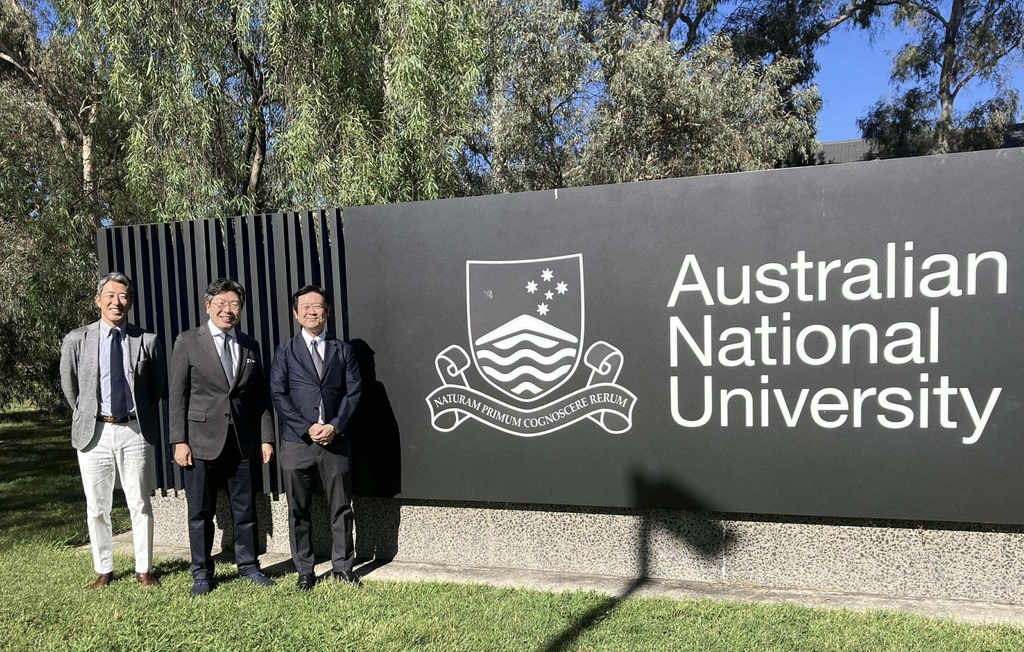
会場となったオーストラリア国立大学
【日豪抑止対話(JADD)】
• JADDでは、「インド太平洋地域の同盟抑止における核兵器の役割の変遷(第1パネル)」、「日豪における通常兵器の攻撃力と抑止力向上(第2パネル)」、「同盟のアーキテクチャー――指揮、統制、調整の課題(第3パネル)」についてパネルを実施。各パネルで、地域の視点、日本の視点、豪州の視点について3名ずつが発表した。議論は「チャタム・ハウス・ルール」にのっとって、非公開でおこなわれた。
• 議論のなかでは、核戦力増強によって中国が核兵器を使用する可能性は高まるのか、ロシアの核政策は中国に影響をおよぼすのかといった問題が提起された。また、米国との拡大抑止、核抑止をめぐっては、2010年代まで豪州(政府)側では関心が低かったとの指摘もあった。
• また、日豪で求められているのは、「more deterrence」なのか「more assurance」なのか、尖閣の事例は中国が日米のレッドラインを理解したことを意味しているのか、日本は反撃能力として弾道ミサイルの保有(+米国との共同生産)も選択肢になるのかなども問われた。能力がそのまま抑止につながるわけではない点や、豪州では外国軍の常駐へのアレルギーがいまだに非常に強い点なども指摘された。また、日豪が目指すべきものとして、「集団的抑止(collective deterrence)」が必要との指摘もあった。

会議の様子
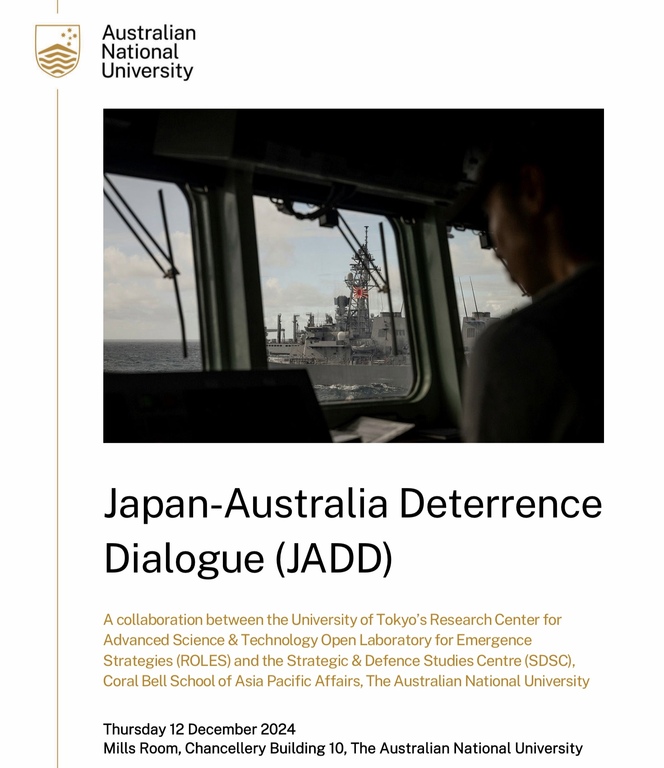
JADDプログラム表紙
【公開セッション】
• JADDの機会に発信の場をつくることを意図して、ANUで「Japan’s new foreign and security Policy directions: Implications for the Japan-Australia partnership」と公開セッションを実施した。司会はLauren Richardson(ANU講師)が務め、JADDに日本側として参加した鶴岡、森、佐竹、寺岡(遠隔)がパネリストとして参加。
• すでに学期の授業も試験も終わり、キャンパスに学生の姿が少なくなっている時期で、集客に懸念があったものの、最終的には30名を超える学生、教員、在豪各国外交団、記者などが出席し、活発な議論がおこなわれた。日本への関心の高さが示される格好になった。
• 2024年10月に日本では石破政権が発足し、11月には米大統領選でトランプ候補が当選するなかで、日米関係や米国の対日、対インド太平洋政策への見方が特に議論になった。日豪協力や日NATO協力も話題になった。
• 世界が激しく動くなかで、日本と豪州に求められる役割がさらに増大していることをあらためて浮き彫りにするセッションだった。今後も、非公開のJADD開催時には、東京でもキャンベラでも(あるいはそれ以外の場所でも)学生や一般向けの公開セッションを実施することが重要だろう。
イベント案内URL:https://www.anu.edu.au/events/japans-new-foreign-and-security-policy-directions-implications-for-the-japan-australia-partnership

イベントの告知HP

イベントの様子
【ASPIでの意見交換】
• 12月13日には、安全保障分野で豪州を代表するシンクタンクである豪戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute: ASPI)を訪問し、Alex Bristow(ASPI上席研究員)、Malcolm Davis(ASPI上席研究員)らとの意見交換をおこなった。
• インド太平洋の安全保障、米トランプ政権の誕生を見据えた課題、日豪協力、AUKUSと日本の協力の可能性などが主に議論になった。日英伊の3カ国で共同開発の進む次期戦闘機GCAPを豪州が導入する可能性や、先進防衛技術協力の枠組みであるAUKUSの第2の柱(Pillar 2)と日本との協力の可能性などが議論になった。

ASPI
実施報告
2024年12月12日、13日(於:キャンベラ)
鶴岡 路人(慶應義塾大学)
【実施目的・背景】
• 日本と豪州はともに米国の同盟国であり、日米間、および米豪間では政府間(トラック1)は当然のこと、民間(トラック2)や政府と民間(トラック1.5)など、さまざまな対話が存在している。しかし、日豪防衛協力が急速に進展するにも関わらず、戦略や抑止に特化した日豪間の確立された政策対話の枠組みは未発達だった。そのため、日豪抑止対話(JADD)を立ち上げる。
• 豪州では、特に政府内において日本留学経験者を含め、日本に詳しい人材が増えているものの、日本側では豪州の政治・外交・安全保障に詳しい人材が政府においてもシンクタンク業界、学界においても不足している。
• 日豪間では、それぞれが有する米国との同盟をいかに管理・発展させられるか、米国政治が大きく変化するなかで拡大抑止の信頼性をいかに維持できるか、米国のインド太平洋関与をいかに維持できるか、日豪が今後強化する長射程のものを含む攻撃能力(日本の場合は「反撃能力」)を同盟の抑止態勢においていかに位置付けるか、NATOや米韓同盟と異なり統合された指揮統制システムがないなかで、日本と豪州は米国との統合をいかに進められるかなど、共通の課題が多数存在している。
• 米英豪の枠組みであるAUKUSをインド太平洋地域や日豪防衛協力においてどのように扱うかも、今後重要な課題になる。全体としては、インド太平洋地域における抑止態勢の強化に日豪がいかに貢献できるかが問われる。
• それらを、単に政策課題として実務的、あるいはジャーナリスティックに議論するのではなく、学問的研究を基礎により深く掘り下げたい。さらにそうした継続的作業を通じて、日豪における政策志向の戦略研究、抑止研究を発展させることが日豪抑止対話の最終的な目的である。
• 「戦略対話」や「安全保障対話」ではなく、あえて「抑止対話」とするのは、テーマの拡散を防ぐためである。ただし、取り上げる課題は狭義の(軍事的な)抑止に限定する必要はなく、広く外交、安全保障、場合によっては経済安全保障や技術に関連するテーマも対象になる。それでも「抑止」という軸を維持し、議論の骨格を維持することを今回の対話の特徴としたい。
【実施形態】
• ROLESで実施中の「『西側』の論理の検証と再構築」研究会(西側研)が母体となり、豪州側について、今回はオーストラリア国立大学(ANU)の戦略・国防研究センター(Strategic and Defence Studies Centre: SDSC)がホストとなり、2024年12月12日にANU内で実施。
• 日本からは、JADD担当の鶴岡路人(慶應義塾大学准教授)の他、いずれも西側研メンバーの森聡(慶應義塾大学教授)、佐竹知彦(青山学院大学准教授)、寺岡亜由美(コロンビア大学研究員・講師:遠隔参加)が出席した。
• 豪州側は、Brendan Taylor(ANU教授、SDSCディレクター)、Stephen Fruehling(ANU教授)をはじめとして、10名以上が参加した。
• セッションは午前に2つ、午後に1つに加え、石破政権下での日本の外交・安全保障政策の展望に関する公開セッションを実施した。
• また、キャンベラ訪問の機会を活用し、翌12月13日には豪戦略政策研究所(ASPI)など訪問し、意見交換をおこなった。また、 JADD実施にあたっての、在オーストラリア日本国大使館からの支援にも感謝したい。
• 初回JADDでの議論を受けて、SDSCのCentre of Gravityシリーズで、日豪のJADD参加者の執筆による、日豪にとっての抑止の課題に関する報告書を2025年中に英語で刊行予定である。同報告書は、その後日本語に翻訳してROLESから刊行する。
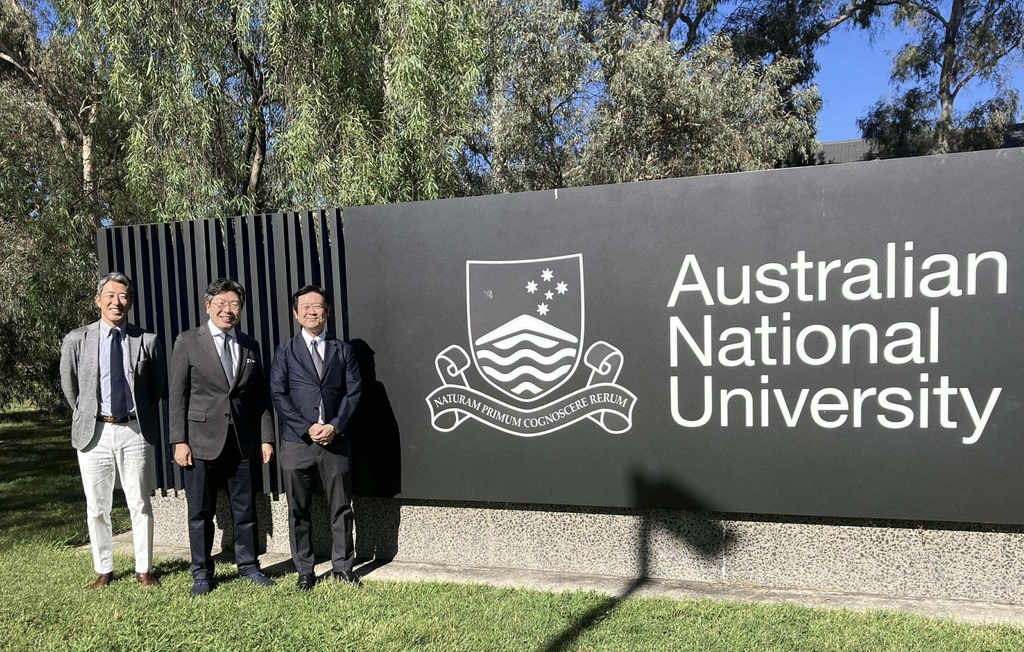
【日豪抑止対話(JADD)】
• JADDでは、「インド太平洋地域の同盟抑止における核兵器の役割の変遷(第1パネル)」、「日豪における通常兵器の攻撃力と抑止力向上(第2パネル)」、「同盟のアーキテクチャー――指揮、統制、調整の課題(第3パネル)」についてパネルを実施。各パネルで、地域の視点、日本の視点、豪州の視点について3名ずつが発表した。議論は「チャタム・ハウス・ルール」にのっとって、非公開でおこなわれた。
• 議論のなかでは、核戦力増強によって中国が核兵器を使用する可能性は高まるのか、ロシアの核政策は中国に影響をおよぼすのかといった問題が提起された。また、米国との拡大抑止、核抑止をめぐっては、2010年代まで豪州(政府)側では関心が低かったとの指摘もあった。
• また、日豪で求められているのは、「more deterrence」なのか「more assurance」なのか、尖閣の事例は中国が日米のレッドラインを理解したことを意味しているのか、日本は反撃能力として弾道ミサイルの保有(+米国との共同生産)も選択肢になるのかなども問われた。能力がそのまま抑止につながるわけではない点や、豪州では外国軍の常駐へのアレルギーがいまだに非常に強い点なども指摘された。また、日豪が目指すべきものとして、「集団的抑止(collective deterrence)」が必要との指摘もあった。

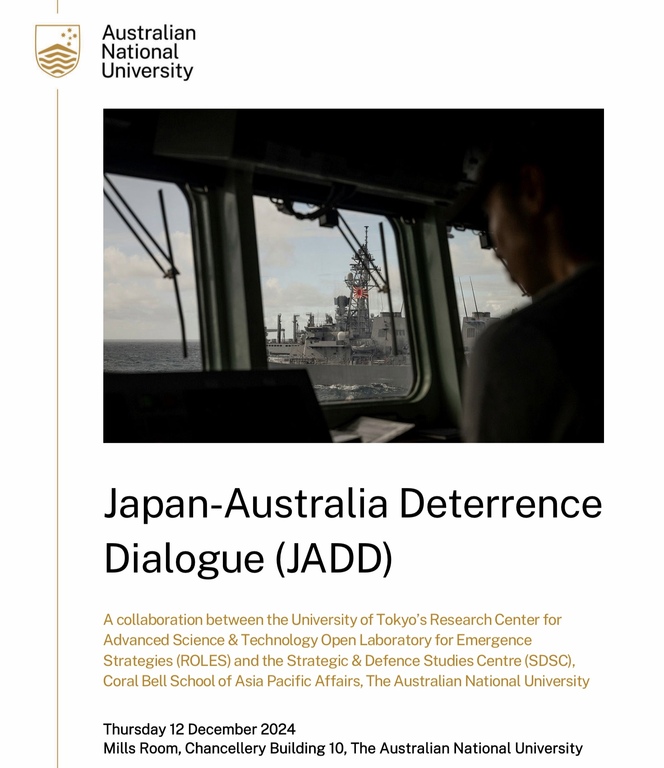
【公開セッション】
• JADDの機会に発信の場をつくることを意図して、ANUで「Japan’s new foreign and security Policy directions: Implications for the Japan-Australia partnership」と公開セッションを実施した。司会はLauren Richardson(ANU講師)が務め、JADDに日本側として参加した鶴岡、森、佐竹、寺岡(遠隔)がパネリストとして参加。
• すでに学期の授業も試験も終わり、キャンパスに学生の姿が少なくなっている時期で、集客に懸念があったものの、最終的には30名を超える学生、教員、在豪各国外交団、記者などが出席し、活発な議論がおこなわれた。日本への関心の高さが示される格好になった。
• 2024年10月に日本では石破政権が発足し、11月には米大統領選でトランプ候補が当選するなかで、日米関係や米国の対日、対インド太平洋政策への見方が特に議論になった。日豪協力や日NATO協力も話題になった。
• 世界が激しく動くなかで、日本と豪州に求められる役割がさらに増大していることをあらためて浮き彫りにするセッションだった。今後も、非公開のJADD開催時には、東京でもキャンベラでも(あるいはそれ以外の場所でも)学生や一般向けの公開セッションを実施することが重要だろう。
イベント案内URL:https://www.anu.edu.au/events/japans-new-foreign-and-security-policy-directions-implications-for-the-japan-australia-partnership


【ASPIでの意見交換】
• 12月13日には、安全保障分野で豪州を代表するシンクタンクである豪戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute: ASPI)を訪問し、Alex Bristow(ASPI上席研究員)、Malcolm Davis(ASPI上席研究員)らとの意見交換をおこなった。
• インド太平洋の安全保障、米トランプ政権の誕生を見据えた課題、日豪協力、AUKUSと日本の協力の可能性などが主に議論になった。日英伊の3カ国で共同開発の進む次期戦闘機GCAPを豪州が導入する可能性や、先進防衛技術協力の枠組みであるAUKUSの第2の柱(Pillar 2)と日本との協力の可能性などが議論になった。

